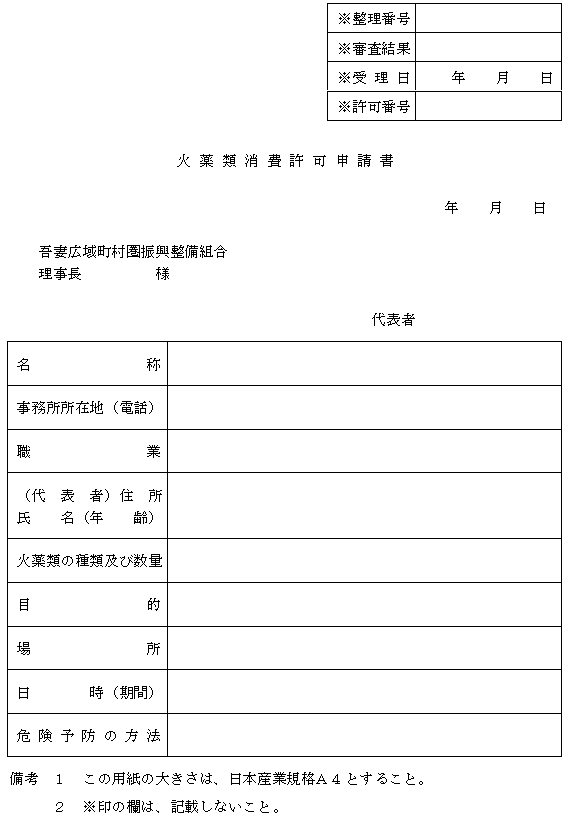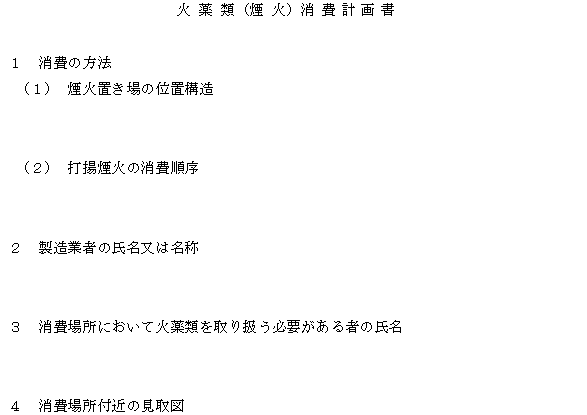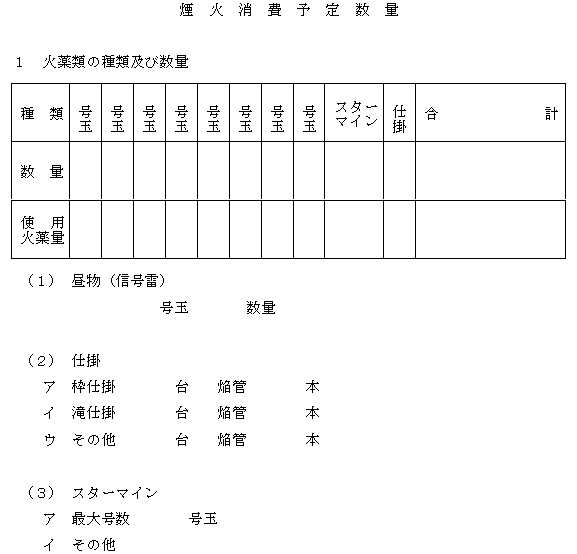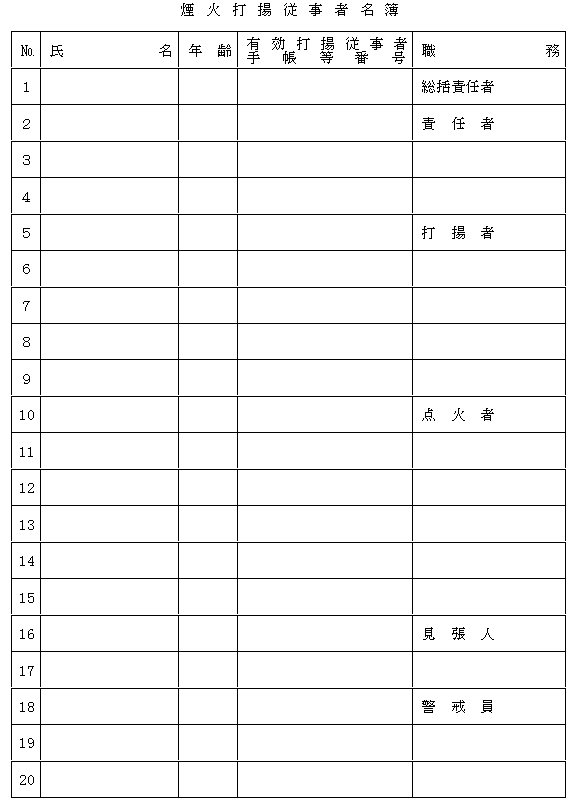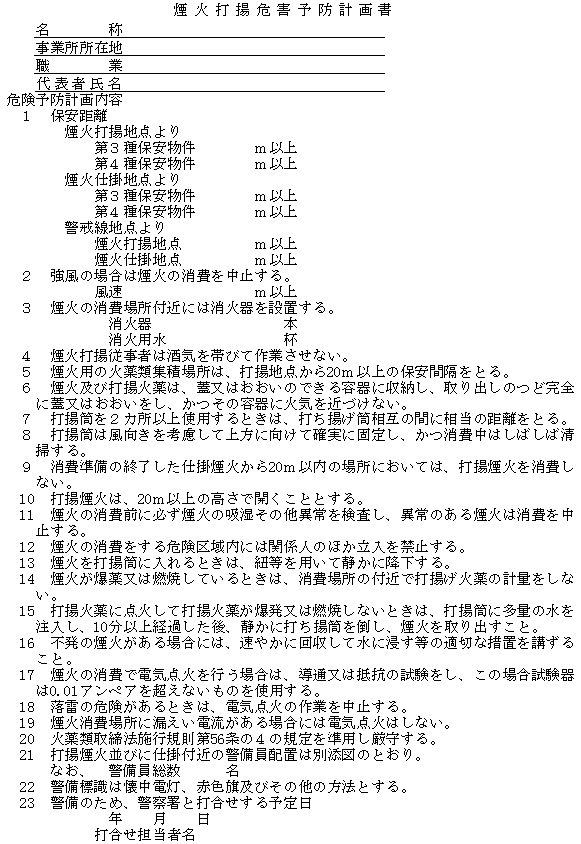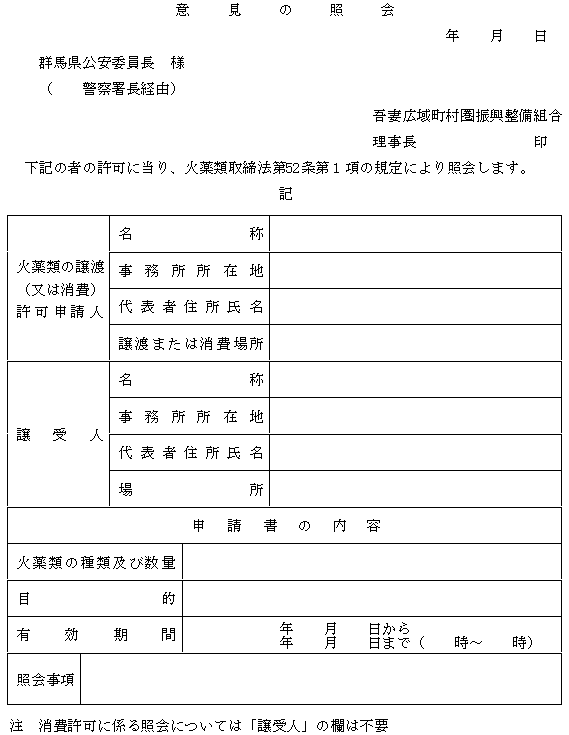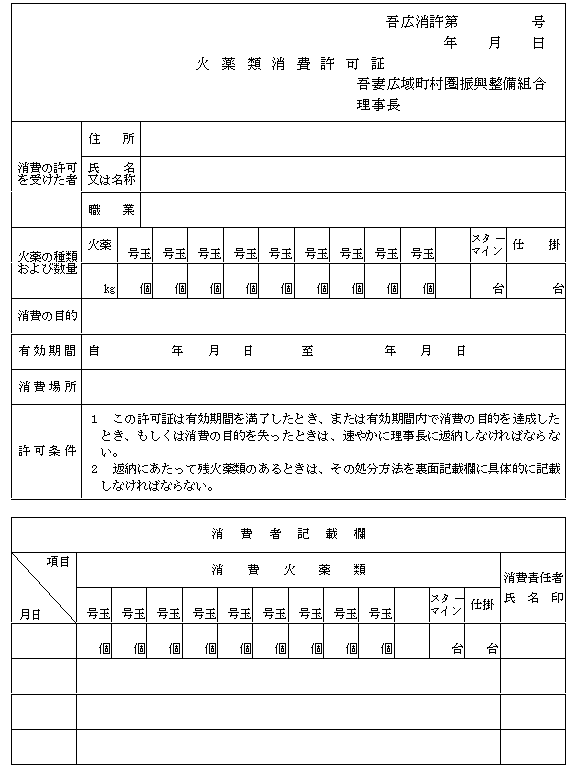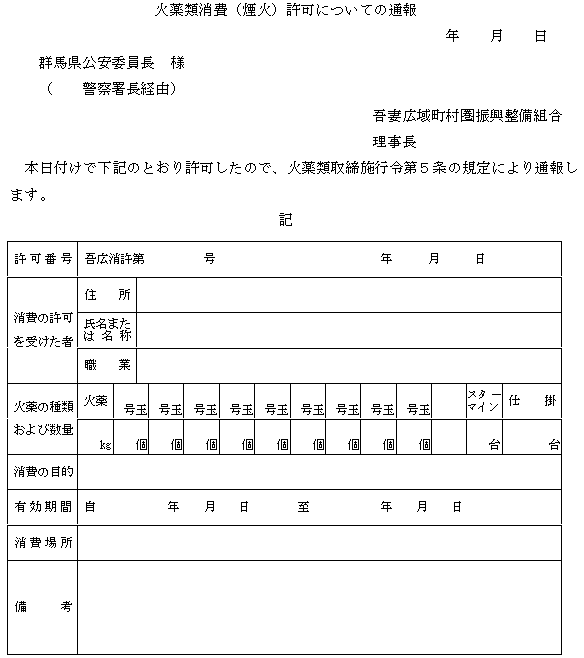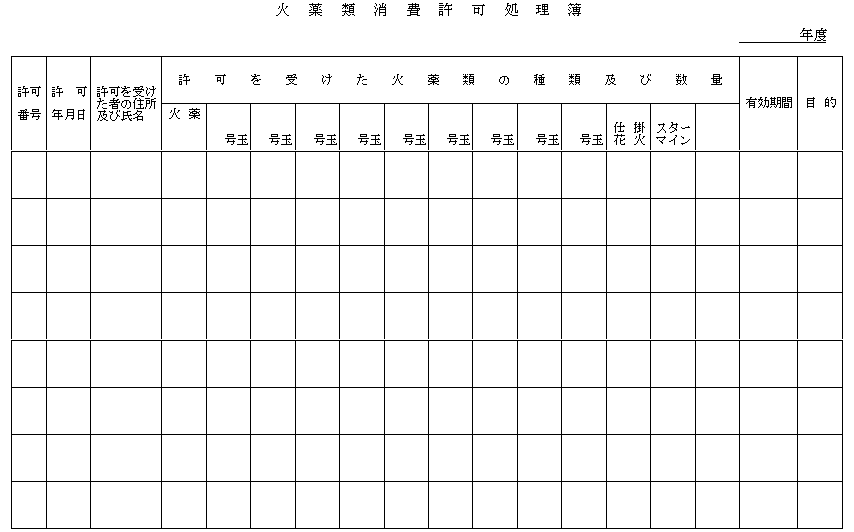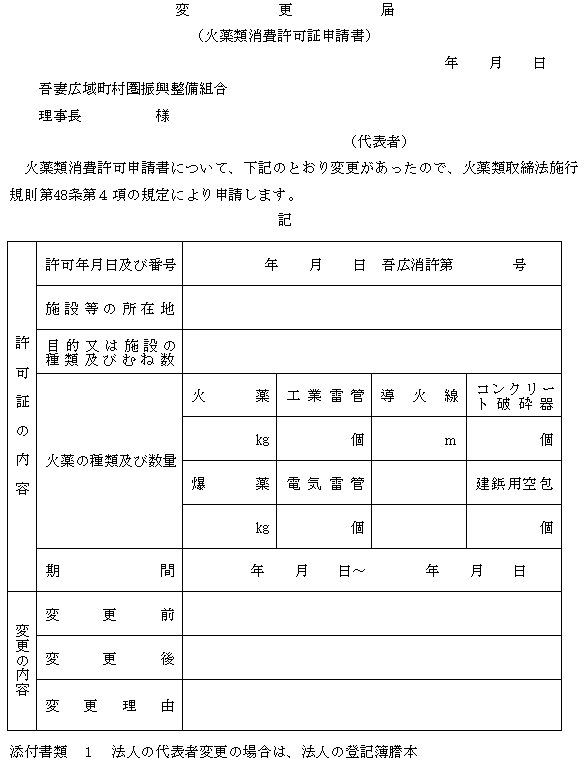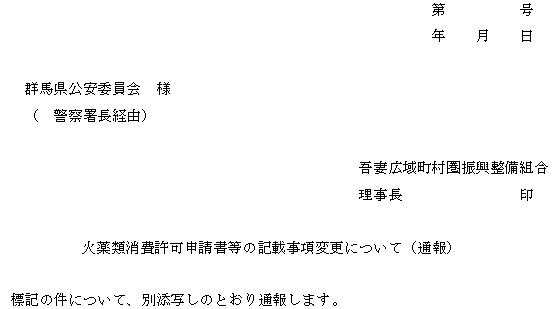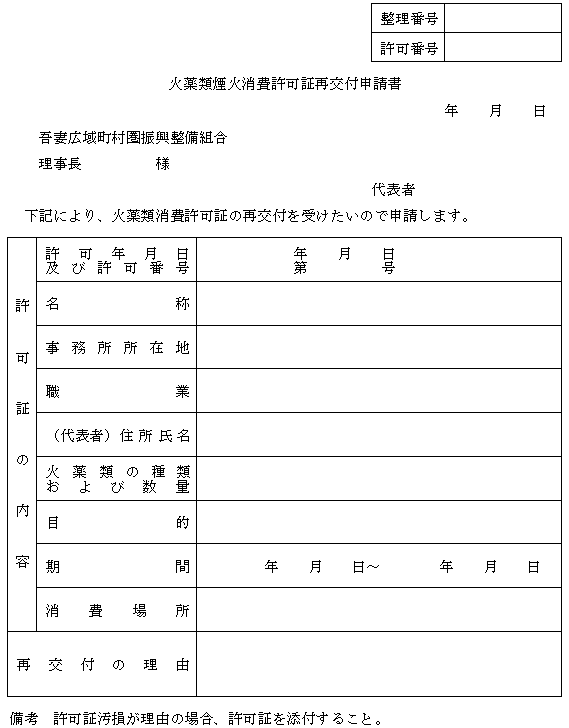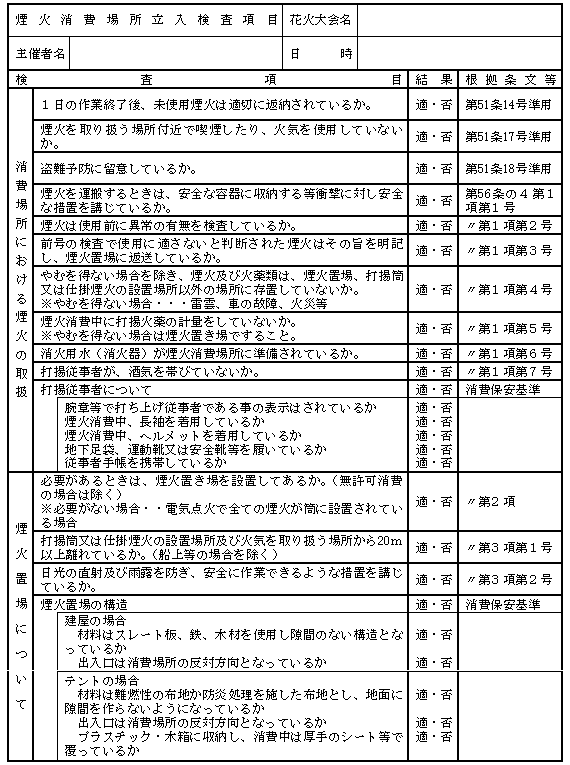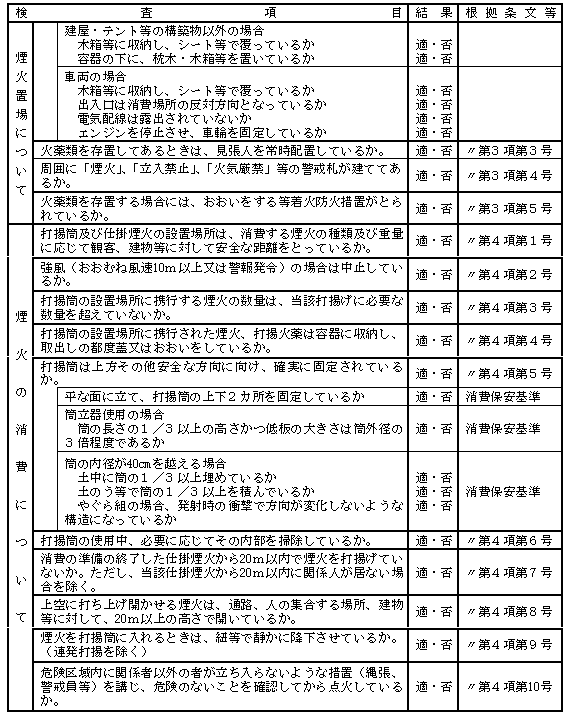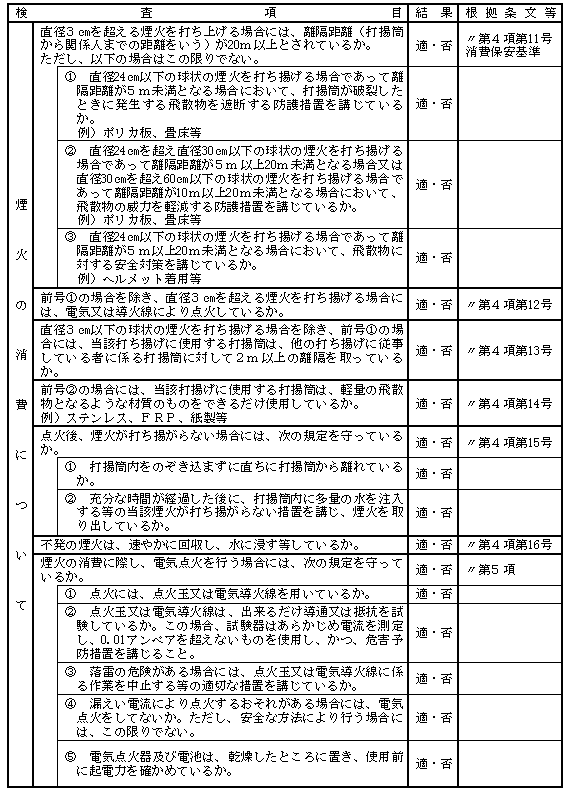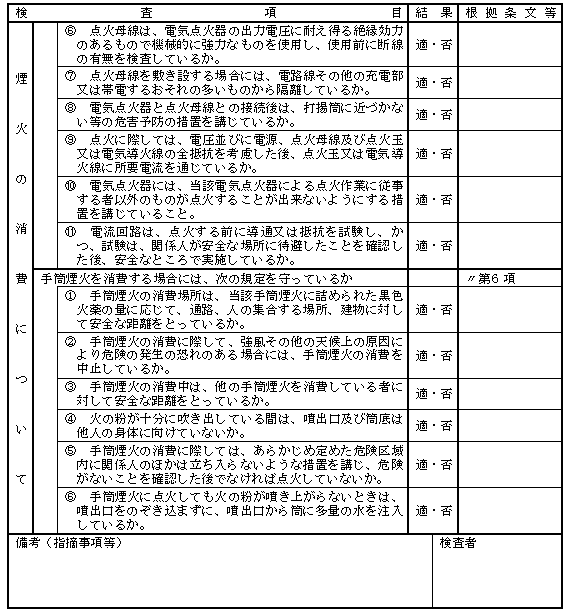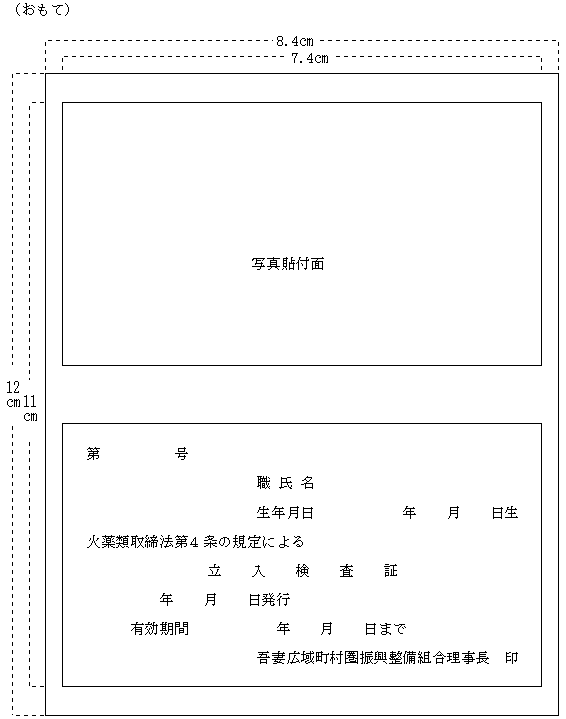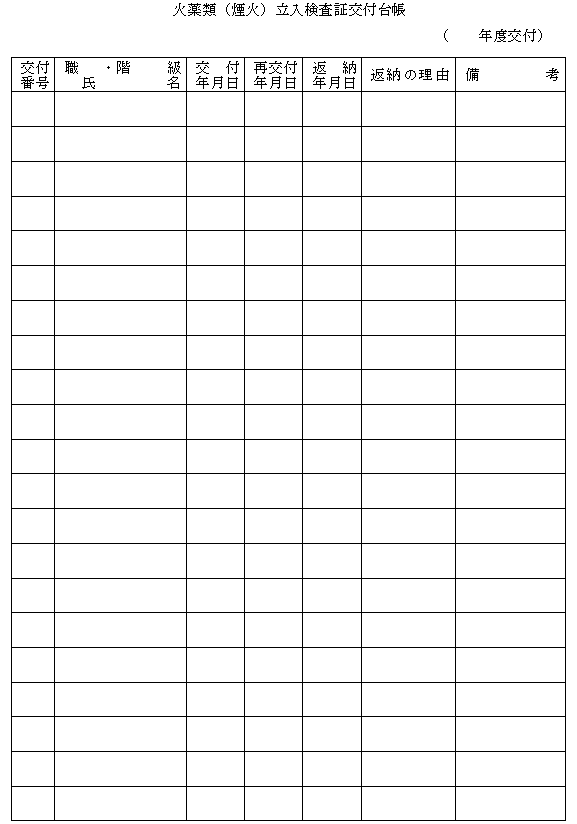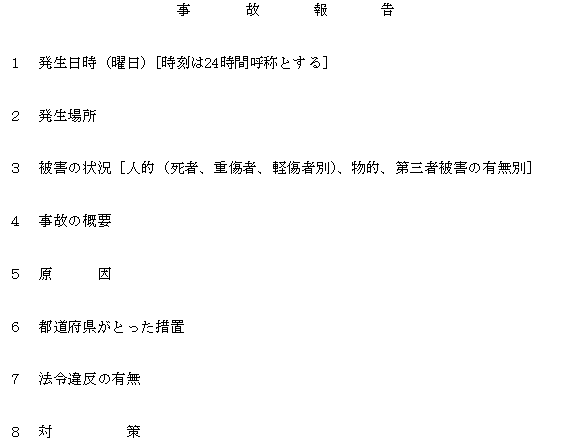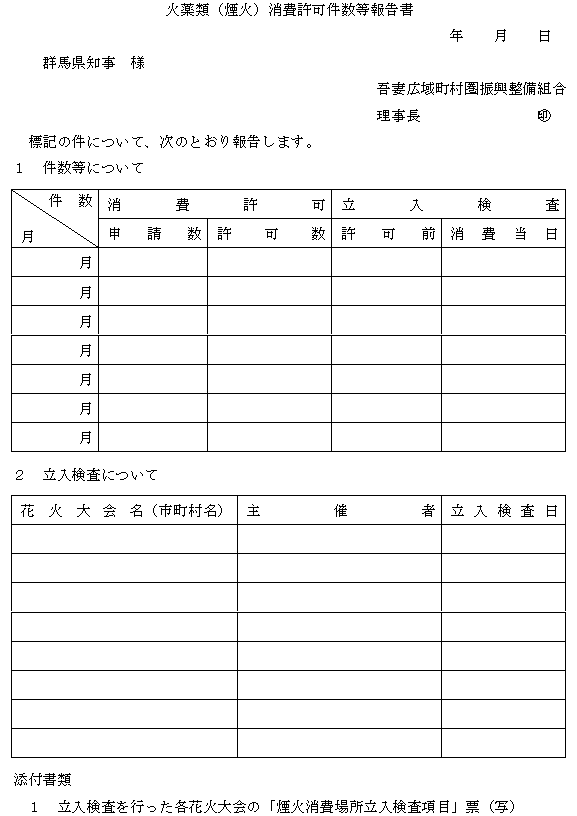��ȍL�撬�����U�������g���Ζ�ގ���@�i���Ώ���j�Ɋւ��鎖�������v�j
����10�N�R���R��
������T��
|
|
|
| ���� | ����13�N�R���P��������S�� | ����18�N�W��18��������19�� |
| ����21�N�R��31��������W�� | �ߘa�R�N10��11��������16�� |
��Q�́@���̏���i��Q���`��W���j
��R�́@���������i��X���`��13���j
��S�́@�G���i��14���E��15���j
��P���@���̗v�j�́A
�Ζ�ގ���@�i�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j�A���{�s�߁i�ȉ��u���߁v�Ƃ����B�j�A���{�s�K���i�ȉ��u�K���v�Ƃ����B�j��ȍL�撬�����U�������g���Ζ����@�Ɋւ��鎖�������K���i�ȉ��u�K���v�Ƃ����B�j�Ɋ�Â��A�Ζ�ނ̎戵���Ɋւ��鎖�������ɂ��ĕK�v�Ȏ������߂�B
��Q���@
�@��25���P���Ɋ�Â����̏���ɌW�鋖�̐\���i�ȉ��u����\���v�Ƃ����B�j�ɂ��ẮA�K����T���Ɋ�Â��Q�n�������ψ���i�ȉ��u�����ψ���v�Ƃ����B�j�̈ӌ������K�v�Ƃ���̂Ō����Ƃ���14���O�ɒ�o��������̂Ƃ���B
�Q�@����\���ɂ������ẮA
�l����P���̉Ζ�ޏ���\�����i�ȉ��u���\�����v�Ƃ����B�j�ɁA���Ɍf����l����Y�t��������̂Ƃ���B
�C�@����ꏊ�t�߂̕ۈ��������̏}
�R�@�O���ɋK�肷�����\���ɂ����ẮA�����Ƃ��ĂP�����o��������̂Ƃ��A�\���҂ɂ����āi�T�j���K�v�ȏꍇ�́A�Q����o��������̂Ƃ���B
�T�@����\���ɂ������ẮA�{�\�����e�ɂ��ďؖ��ł���҂ɂ�������̂Ƃ���B�Ȃ��A�����Ƃ��ėX���ł̐\���͎�t���Ȃ����̂Ƃ���B
�U�@�\�����́A���N�M�A�{�[���y�����Ő��m�ɋL��������̂Ƃ���B
�V�@���\�����A�ŗg���Ώ]���ґS���̎蒠���͎蒠�̎ʂ��i�R�s�[�j�����Q�����m�F������̂Ƃ���B
��R���@����\������R������ɂ������ẮA���̊e���Ɍf������e�ɂ��s�����̂Ƃ���B
�A�@��\�Ҏ������ɂ́A��Î҂��c�̂̏ꍇ�͒c�̖��Ƒ�\�҂��L�����A�c�̈͑�\�҈�̉����邱�ƁB�������A�l�̏ꍇ�͎������L�����A�l�̉����邱�ƁB
�C�@���́A�E�Ɨ��ɂ́A�c�̂̏ꍇ�͒c�̖��𖼏̗��ɁA�E�����E�Ɨ��ɋL������Ă��邱�ƁB�l�̏ꍇ�́A�����������̗��ɋL������Ă��邱�ƁB
�E�@���̎�ދy�ѐ��ʗ��ɂ́A
�l����Q���̉Ζ����v�揑�̏���鉌�̎�ށA���ʂƍ��v���Ă��邱�ƁB
�G�@�ړI���ɂ͉ԉΑ��A�Ղ̏ꍇ�͂��̑��A�Ֆ��������m�ɋL������Ă��邱�ƁB
�I�@�ꏊ���ɂ́A����ꏊ�̏Z�������m�ɋL������Ă��邱�ƁB
�J�@�������ɂ́A�J�V�������̏ꍇ�͗\��N�������L�����A�����̏ꍇ�͂��̊��Ԃ��L������Ă��邱�ƁB�������A�����E�����̊��Ԃ͂V���ȓ��Ƃ����̊��Ԃ��o�߂����Ƃ��́A���߂ď���������邱�ƁB
�L�@�A����J�܂łɌf������̂̂ق��A���Y���\�����̐R���ɍۂ��ẮA�\���҂ɑ������x�@���Ƌٖ��ȘA����ۂ��A����ɖ��S���������邱�ƁB
�A�@���Βu��̈ʒu�\���������m�ɋL������Ă��邱�ƁB
�C�@�ŗg���̏���������m�ɋL������Ă��邱�ƁB
�E�@�����Ǝ҂������̏ꍇ�͂��̏�ʂR�Ђ܂ł��L�������邱�ƁB
(�A)�@�}�́A�s�̂̏Z��n�}�𗘗p�������̂ł悢�B
(�C)�@�}�ɂ́A�����֎~��ԁA�ʍs�~��ԁA�����l�z�u�ʒu�A�ۈ��������L������Ă��邱�ƁB
(�E)�@�ŗg�ʒu���݂̋������L������Ă��邱�ƁB
(�G)�@�O(�A)����(�E)�܂łɌf������̂̂ق��A���n�ł͗����֎~���Ƀ��[�v��A�����֎~�D�𗧂Ă�ȂǁA�l���e�Ղɗ������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�Ɏw�����邱�ƁB
(�A)�@�ŗg���A�X�^�[�}�C���̍ő卆���̕ۈ������̉~�Ƃ��̕t�߂̕ۈ��������L������Ă��邱�ƁB
(�C)�@�ŗg�ꏊ�A���Βu��A�d�|�ԉi�X�^�[�}�C���A��j���̈ʒu�Ƃ��̋������L������Ă��邱�ƁB
(�E)�@�����֎~��ԁA�ϗ��҈ʒu����������Ă��邱�ƁB
�A�@����y�ѐ��ʗ��ɂ͎��̂悤�ȓ��e���L������Ă��邱�ƁB
(�A)�@��ޗ��ɂ͑ŗg���̎�ނ��L������Ă��邱�ƁB
(�C)�@���ʗ��ɂ͂��ꂼ��̏���ʂ��L������Ă��邱�ƁB
(�E)�@�g�p�Ζ�ʗ��ɂ́A���˖�Ƃ��Ďg�p����Ζ��A�d�C�_���s���ꍇ�Ɏg�p����_�ʓ��̐��ʂ��L������Ă��邱�ƁB
(�G)�@�d�|���ɂ͊e��d�|�ԉ̐��ʂ��L������Ă��邱�ƁB
(�I)�@�X�^�[�}�C�����ɂ́A���̒��̍ő卆�����L������Ă��邱�ƁB
�A�@���Αŗg�]���Җ���̍쐬�ɂ������ẮA���Αŗg�]���Ҏ蒠���ԍ����ɂ͎擾�蒠�̔ԍ����L������Ă��邱�ƁB
�C�@�E�����Ɋe�E�����L�����Ă��邱�ƁB
�E�@�蒠�Ƃ̏ƍ��͕K���s���A�����A��u�N�������̊m�F���s�����ƁB
�A�@�ۈ��������ɂ́A���Αŗg�ꏊ�A���Ύd�|�A�x�����n�_���A���ꂼ��̕ۈ��������ۂ���Ă��邱�ƁB
�C�@�T�˕���10���ȏ�̏ꍇ���Ώ���𒆎~�����邱�ƁB
�E�@����ꏊ�ɏ��Ί퓙�̏��Ί��ݒu����Ă��邱�ƁB
��S���@���ɌW��W���������Ԃ́A�����Ƃ��ĂV���ԂƂ���B�������A�K����T���P����i�̋K��Ɋ�Â��Q�n�������ψ���ւ̈ӌ����悪�K�v�ȏꍇ�́A���̌���łȂ��B
�Q�@�O���̌Q�n�������ψ���ւ̈ӌ�����́A
�l����U���̉��̏���Ɋւ���ӌ��̒���ɂ��Ăɂ��A���\�����̎ʂ���Y�t���čs�����̂Ƃ���B
�R�@�K����T���Q���Ɋ�Â�������t����Ƃ��́A
�l����V���̉��Ώ���ɂ��A�K�v�ɉ����������Č�t������̂Ƃ���B
�S�@�O���̉��Ώ������t�����Ƃ��́A
�l����W���̉Ζ�ޏ���i���j���ɂ��Ă̒ʕ�ɂ��A�Q�n�������ψ���֒ʕ���̂Ƃ���B
�T�@��R���̉��Ώ������t����Ƃ��́A���̋����e���ɂ���
�l����X���̉��Ώ��������ɋL�ڂ��Ă������̂Ƃ���B
�U�@�K����T���S���̋K��Ɋ�Â��A�\���҂ɑ����ł��Ȃ��|��ʒm����ꍇ�́A�Q�n�����h�h�ЉۂƋ��c�̂����s�����̂Ƃ���B
�V�@�K����U���P���̋K��Ɋ�Â��A�\���҂ɑ����̎�������s���ꍇ�́A�Q�n�����h�h�ЉۂƋ��c�̂����s�����̂Ƃ���B
�W�@�O���̋��̎�������s�����ꍇ�ɂ�����A�K����U���Q���̋K��Ɋ�Â��Q�n�������ψ���ւ̒ʕ�́A�Q�n�����h�h�ЉۂƋ��c�̂����s�����̂Ƃ���B
�i����\�������̋L�ڎ����̕ύX�́j
��T���@�K����V���Ɋ�Â��A����\�����y�щΖ�ޏ���v�揑�̋L�ڎ����ɕύX���������Ƃ��́A�\���҂ɑ��A
�l����10���̕ύX�́i�Ζ�ޏ���\�����j�ɂ��A�͏o��������̂Ƃ���B
�Q�@�K����V���Q���Ɋ�Â��A�Q�n�������ψ���ւ̒ʕ�́A
�l����11���̉Ζ�ޏ���\�����̋L�ڎ����ύX�ɂ��āi�ʕ�j�ɂ��A�s�����̂Ƃ���B
��U���@�K����W���Ɋ�Â��A���Ώ���̍Č�t�\�����s���ꍇ�́A
�l����12���̉Ζ�މ��Ώ���؍Č�t�\�������o��������̂Ƃ���B
�Q�@�O���̏ꍇ�ɂ����鉌�Ώ���́A��S���R���ɏ�������������̂Ƃ��A���Y���̓K���Ȉʒu�ɁA�鏑���ōČ�t�ƋL������̂Ƃ���B
��V���@���̏���ɌW���́A
�ʋL�P�̂Ƃ���Ƃ���B
��W���@���Ώ���̕ۈ�������́A
�ʋL�Q�̂Ƃ���Ƃ���B
��X���@�K����X���P���̋K��Ɋ�Â������������s���ꍇ�A���̏���ꏊ���ɂ����Ă�
�l����13�����̂P�y�т��̂Q�̉��Ώ���ꏊ�����������̓��e�ɂ�茟�����s�����̂Ƃ���B
��10���@�K����X���P���Ɋ�Â�����ꏊ���͕ۊǏꏊ�̗����������s�������ʁA�@�ߓ��Ɉᔽ���Ă���ƔF�߂���ꍇ�́A�������P���w��������̂Ƃ���B���̏ꍇ�ɂ����āA�d��Ȉᔽ����������ꍇ�ɂ́A�Q�n�����h�h�ЉۂƏ\���ȋ��c���s�����̂Ƃ���B
��11���@�K����X���Q���̋K��Ɋ�Â��A�������i�E���j���g�т���
�l����14���̗��������͏��h������t����B
�Q�@���h���́A�O���̗�����������t����ꍇ�A�����ے��ɍ쐬��������̂Ƃ���B
�R�@�����ے��́A�O���ɂ�藧���������쐬����ꍇ�A
�l����15���̉Ζ�ށi���j���������،�t�䒠�ɕK�v�������L�ڂ�����A�����������e�������ɑ��t������̂Ƃ���B
�S�@���������́A�T�N���ƂɍX�V������̂Ƃ��A���̗v�̂͑O�e���ɏ�������̂Ƃ���B
��12���@���������̌�t�����E���́A���������𑼐l�ɏ��n���A�Ⴕ���͑ݗ^�����͎g�p�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�Q�@���������̌�t�����E�������������������Ƃ��́A�����ɏ��h�{���\�h�ے��A�����y�я������i�ȉ��u�e�������v�Ƃ����B�j�ɓ͏o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�R�@�e�������́A���������̌�t�����E�������13���̗��������̕��������|�̓͏o���������Ƃ��́A�����ɏ��h���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�S�@�e�������́A�O���̓͏o�����������̍Č�t���悤�Ƃ���ꍇ�́A���h���ɕ����ɂ��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�T�@���h���́A�O���̏��u��A�Č�t���邱�Ƃ��K���ƔF�߂��ꍇ�A�����ے��ɗ��������̍Č�t�𖽂��邱�Ƃ��ł���B
��13���@�e�������́A���������E�����ސE���ɂ�藧��������K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ����Ƃ��́A���Y�E�����璼���ɗ���������Ԕ[��������̂Ƃ���B
�Q�@�e�������́A�E���Ɍ�t����Ă��闧���������L�����Ԃ��߂����Ƃ��́A�����ɕԔ[��������̂Ƃ���B
�R�@�����ے��́A�O�e���ɂ��Ԕ[�ʒm���������Ƃ��́A���������،�t�䒠�𑬂₩�ɏC�����Ă������̂Ƃ���B
��14���@�K����17���Ɋ�Â��A���̂̓͏o���s�킹��ꍇ�́A
�l����16���̉Ζ�ށi���j���̕��ɂ����̂Ƃ���B
�Q�@�K����17���Ɋ�Â��ЊQ�����̕��́A�ЊQ�������o�m�����ꍇ�A���₩�ɌQ�n�����h�h�Љۂɒʕ���̂Ƃ��A���̌�̏��u�ɂ��Ă͉Ζ�ގ��̑[�u�v�j�i���a51�N�ʏ��Y�Əȗ��n���Q�Ǖۈ��ہj�y�ю��̏����x�i�����R�N�V��22���ʏ��Y�Əȗ��n���Q�Ǖۈ��ۉΖ�ǁj�ɏ����ČQ�n�����h�h�ЉۂƋ������Ă��̑[�u�ɂ�������̂Ƃ���B
��15���@�Ζ�ށi���j������̏����������A
�l����17���̉Ζ�ށi���j������������ŁA�N�Q��Q�n���m���i���h�h�Љیo�R�j�ɕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�@�S������W���܂ł̏����ɂ��Ă͂X��15���܂ŁA�X�����痂�N�R���܂ł̏����ɂ��Ă͂S��15���܂łɕ�����̂Ƃ���B
���̗v�j�́A����10�N�S���P������{�s����B
���@��
�i����13�N�R���P��������S���j ���̗v�j�́A����13�N�S���P������{�s����B
���@��
�i����18�N�W��18��������19���j ���̗v�j�́A���z�̓�����{�s����B
���@��
�i����21�N�R��31��������W���j ���̗v�j�́A����21�N�S���P������{�s����B
���@��
�i�ߘa�R�N10��11��������16���j ���̗v�j�́A���z�̓�����{�s����B
�A�@�ۈ������Ƃ͎��̂��̂������B�i�Q�n���Ζ�ގ���w���v�j��蔲���j
|
|
��� | �Y�����镨�� |
��P��ۈ����� | �������A�s�X�n�̉Ɖ��A�w�Z�A�ۈ珊�A�a�@�A�w�Z�A����A���Z��A�Ў��A���� |
��Q��ۈ����� | �����̉Ɖ��A���� |
��R��ۈ����� | �Ɖ��i��P�햔�͑�Q��ۈ������̑�������̂������B�j |
�S���A�O���A�Ζ��^���N�A�K�X�^���N�A���d���A�ϓd���A�H�� |
��S��ۈ����� | �����A�s���{�����A�����d���A�Ζ�ގ戵���A�C�̎戵�� |
�C�@�Y�����镨���̉��߂͎��̒ʂ�ł���B
(�A)�@�s�X�n�̉Ɖ��\�@�Љ�ʔO��s�X�n�ƌ����ɂӂ��킵�����x�ɑ������i���ʒ��x�̉Ɖ������ނ�100���ȏ�j������A�˂Ă���Ɖ��̏W�c�������B�s�A���A�����̍s�����A�Z���̋ƑԂƂ͊W�Ȃ��B
(�C)�@�w�Z�\�@
�w�Z����@��P���̊w�Z�A����82���̂Q�̐��w�Z�y�ё�83���̊e��w�Z�������B
(�I)�@����\�@��݂̌���������B���݂̂��̂͊܂܂Ȃ��B
(�J)�@���Z��\�@�������̊ϋq�����e����{�݂̂��鋣�Z��������B
(�L)�@���Ћy�ы���\�@�������̎Q�q�҂����鎛�ЁA���@�y�ы���������B�R�_�A�K���͊܂܂Ȃ��B
(�N)�@�����̉Ɖ��\�@�Љ�ʔO�㑺���Ƃ����̂ɂӂ��킵�����x�ɑ������i���ʋK�͂̉Ɖ������ނ�10���ȏ�100�������j���Q���Ȃ��Ă���Ɖ��������B�s�����A�Z���̋ƑԂƂ͊W�Ȃ��B
(�P)�@�����\�@�펞�������̐l���o���肷������������B���R�����͊܂܂Ȃ����A���������⍑������̓��ʒn��͕ۈ������̑ΏۂƂȂ�B
(�R)�@�Ɖ��\�@�l��������������ɂ킽���ċ��Z�A�Ζ��܂��͏o���肷��Z�ƁA�������A�X�܁A�}���ق��̑������ɗނ��錚�z���������B�q�ɁA���u�A�X�ɓ��͊܂܂Ȃ��B
(�T)�@�S���A�O���\�@�S���y�сi�l���^�����鎖��ړI�Ƃ��Ȃ����̂������B�j
�O���@��P���̋O���i�l���^�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ȃ����̂������B�j�������B���Ȃ킿�S���͂��ׂĕۈ������ƂȂ邪�A�n���S���@�̓S����
�O���@�̋O���ɂ��ẮA��p�̋O���y�ѓS���̂����ݕ��݂̂��^�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����͕̂ۈ��������珜�����B
(�V)�@�Ζ��^���N�\�@�Ζ��ށi
���h�@��10���ʕ\�ł�����P�Ζ��ނ����S�Ζ��ށj�����邽�߂̃^���N�B�܂��A�n���E�n�㓙�ݒu�ɂƂ��ꂸ�A�ۈ������Ƃ���B�i�Ȃ��A�ۈ������Ƃ��Ă̐Ζ��^���N�A�K�X�^���N���Ƃ́A�Љ�ʔO��̃^���N�������A�ʏ�A�Ζ���ЃK�X��Г��ɂ��鑊���K�͂̃^���N�������B�j
(�X)�@�����d���\�@�d�C�ݔ��Ɋւ���Z�p����߂�ʎY�ȗ߁i���a40�N�ȗߑ�61���j��R���ɋK�肷����ʍ����i7,000�u������́j�d���������B
(�Z)�@�Ζ�ގ戵���\�@
�Ζ�ގ���@���K�p�����y�،���A�̐Ώꓙ�݂̂łȂ��A
�z�R�ۈ��@�̓K�p�����z�R�ɂ�����Ζ�ގ戵�����܂܂��B
(�\)�@�C�̎戵���\�Α���A�b�艮�A�o�H�ċp�ꓙ�������B
�i�Q�n���Ζ�ގ���w���v�j��蔲���j
|
|
|
|
|
|
|
|
| �R���� | �S���� | �T���� | �V���� | 10���� | 20���� | 30���� |
������ | �X�p | 12 | 15 | 21 | 30 | 60 | 90 |
���B���x | 130�` | 175�` | 220�` | 250�` | 350�` | 450�` | 550�` |
�i���j | 180 | 210 | 280 | 290 | 380 | 490 | 650 |
�J�����a | 40�`50 | 50�`60 | 75�`100 | 100�` | 140�` | 250�` | 300�` |
�i���j | | | | 130 | 180 | 285 | 350 |
�ʂ̏d�� | 0.2 | 0.5 | 0.9�` | 2.5�` | 7.5�` | 45�` | 200�` |
�i�s�j | | | 1.2 | 3.0 | 9.0 | 60 | 300 |
�ŗg�Ζ�� | 20 | 40 | 75�` | 180�` | 500�` | 3,800�` | 15,000 |
�i���j | | | 100 | 200 | 600 | 4,900 | |
�ʋL�R
�@�����Ȃ��ŏ���邱�Ƃ��ł���Ζ�ނ̗p�r�y�ѐ��� (�P)�@�M�����͊Ϗ܂̗p�ɋ����邽�ߏ���鉌�i�K����49���S���j
�@�@����̑ŗg���i�~���`�͑ΏۊO�j
���a�U�p�ȉ��̋ʁi�Q���ʈȉ��j�@50�ȉ�
���a�U�p��10�p�ȉ��̋ʁi2.5���`�R���ȉ��j�@15�ȉ�
���a10�p��14�p�ȉ��̋ʁi3.5���`�S���ȉ��j�@10�ȉ�
�i���j�ʂ̍����͂����܂ł��ڈ��ł���A�����Ŕ��f����̂łȂ��A�ʂ̒��a�i�p�j�Ŕ��f����B�i�P�����R�p�Ƃ���B�j
���A�F�Γ����o������200�{�ȉ���ؖ��͒|�ō��ꂽ�G�^���Ɏ�t�A���ΐ��i���ΐ��̈��ŁA�R��15���^�b�j�łȂ��B��Ăɓ_���ĕ����A�G�������A���̓��[�v�ɉ̕�����Ƃ��鉋��200�{�ȉ���݂��āA�R�`�A�ꓙ��\�����́B
�ȏ�Q��ނ̎d�|���̂����P��ȉ�������ʂƂ���B
�������A�g���R�ɕ����u���{��v�ƘA�����Č�����ꍇ�́A���ǂ�200�{�ȉ��ł���P��̎d�|���Ƃ݂Ȃ����B
�B�@�t�@�C���[�N���b�J�[���͔��|
�Ζ�P���ȉ��A����0.1���ȉ��̃t�@�C���[�N���b�J�[300�{�ȉ��A�t�@�C���[�N���b�J�[30�{�ȉ���A���������|300�ȉ�
�C�@���Z�p���ǁi�^����̃X�^�[�^�[�̃s�X�g���p���̂��́j
�D�@��������ɌW���ށA���ʓ��ɂ���
�A�@��̖ړI�i�^����A���Ղ蓙�̍��}�p�j�̂��߂ɏ����@����C�Ɍf�����i��A���ʂ̍��v���P���ɏ���邱�Ƃ��ł���B
�C�@����ʂ��A�S���ʂ��R���Ȃ����ĂQ���ʂ�10�������铙�̊��Z���ď���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�E�@���ʂ̓X�^�[�}�C���̂悤�ɘA�����ɂ��ď���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�G�@�����̖�ʂ�����I�[�o�[�������̓��ł����鏬�^���Ə̂�����̂̒��ɁA�����o�����́A�̕����o��������́A������ł��g������́A�ʁA��������ł��グ����̂�A�p���V���[�g��������B�����̂��̂͑ŗg���ΈȊO�̎d�|���ɑ�����̂Ŗ{���Œ�߂閳������ʂ̕i�ڂɂ͓���Ȃ��B
�܂��A���ʂƓ����悤�ɋʊk�ɐ��○�����l�߂����˓����\�{�A���S�{�ƘA�����Ėؔ��A�i�{�[�������ɌŒ肵�A�e���ΐ��ŘA���������̂����邪�����̂��̂��ŗg���ΈȊO�̎d�|���ƌ��Ȃ����̂ŁA�{���̖�������i�ڂɂ͓���Ȃ��B���ď���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
(�Q)�@�f��Ⴕ���͉����A���y��̉��o�̌��ʂ̗p�ɋ����鉌��
�{���Ŗ�������ł���͈͂́A�f��A�����ԑg�̐���A�����A���y���̑��̌|�\�̌����A�X�|�[�c�̋��s���͔�����̉��o�̌��ʂ̗p�ɋ����邽�߂ɉ��i�ŗg���������B�j�������ꍇ�ɂ́A����̏���n�ɂ����Ĉ���ɂ����̌������Ȃ��Ζ�Ⴕ���͔����p�������i�ŗg���������B�j
���̌������Ȃ��Ζ�Ⴕ���͔���̗�
15����30���ȉ��̉��@30�ȉ�
30����50���ȉ��̉��@�T�ȉ�
���͔������A�B�e�p�Ɩ����Ⴕ���͔���i���������o�����߂̂��̂Ɍ���B�j0.1���ȉ��̉������ɏ���ł���B
�{���Ɍf�����Ă��鉌�́A�������A�B�e�p�̏Ɩ����ȊO�͍\������肵�Ă��Ȃ��B�܂��A�Ζ�A����̎g�p�敪���߂Ă��Ȃ��̂Ŕ���݂̂��g�p�������̎戵���ɂ��ẮA���ӂ���K�v������B
�A�@�{����K�p�ł�������ɂ��āi�����W�N�R��29���W���Ǒ�195���ʎY�Ȓʒm�j
�A�@�u�f��Ⴕ���͕����ԑg�̐���v�Ƃ́A�f��A�e���r�ԑg�̖{�ԎB�e�̂ق��A�e�X�g�E���n�[�T�����܂ނ��̂Ƃ���B
�C�@�u�����A���y���̑��̌|�\�̌����v�Ƃ́A����A��O���ꓙ�̕���Ɗϋq�Ȃ����m�ɋ敪����Ă�����̎{�݂ɂ����čs�������A���t�A�����A���|�ł����āA��Î҂����m�Ɍ��܂��Ă��āA�����Ƃ��ė�����������̂Ɍ���B����āA������A�w�Z���ŊJ�Â��鉉�|��A�w�|��Ȃǂ̗L�u�ɂ���ĊJ�Â������̂́u�����v�Ɋ܂܂�Ȃ��B
�E�@�u�X�|�[�c�̋��s�v�Ƃ́A���Z��A���Z�{�ݓ��ɂ����čs����X�|�[�c�̎����A���Z��A���ł����āA���̎�Î҂����m�Ɍ��܂��Ă��āA�����Ƃ��ė�����������̂Ɍ���B����āA������A�w�Z���ŊJ�Â���鋣�Z��A�^����Ȃǂ̗L�u�ɂ���ĊJ�Â������̂́A�u���s�v�Ɋ܂܂�Ȃ��B
�G�@�u������̑�����ɗނ���Â��v�Ƃ́A������A�W����A�W����ł����āA���̎�Î҂����m�ɒ�܂��Ă�����̂������B
�I�@���ׂāA���o�̌��ʂɋ�����ꍇ�Ɍ����A���̏���Ϗ܂��傽��ړI�Ƃ�����̂͊܂܂Ȃ��B
��������Ɋւ���u����̏���n�v�̈Ӗ��͏���ꏊ�̊ϔO�����L�����̂ŁA���̉��̏���ɂ���āA�M�����͊Ϗ܂̖ړI��B���邱�Ƃ��ł���͈͂�ڎw�����̂ł���B
�Ⴆ�A�_�Ђ̍�ŎQ���̓����ɓ��ꂪ�����āA���̉@�߂��ɂ����ꂪ����ꍇ�ɂ����āA������̋��������Ƃ��Q�q�ȏ㗣��Ă����Ƃ��Ă��A�����̓���͓���̏���n�ɂ�����̂ƌ��Ȃ��A������ŏ����鉌�̍��v������ʈȉ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�l����P��
�i��Q���W�j 
�l����Q��
�i��Q���W�j 
�l����R��
�i��Q���W�j 
�l����S��
�i��Q���W�j 
�l����T��
�i��Q���W�j 
�l����U��
�i��S���W�j 
�l����V��
�i��S���W�j 
�l����W��
�i��S���W�j 
�l����X��
�i��S���W�j 
�l����10��
�i��T���W�j 
�l����11��
�i��T���W�j 
�l����12��
�i��U���W�j 
�l����13��
�i��X���W�j 
�l����14��
�i��11���W�j 
�l����15��
�i��11���W�j 
�l����16��
�i��14���W�j 
�l����17��
�i��15���W�j